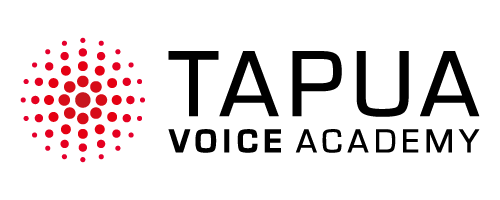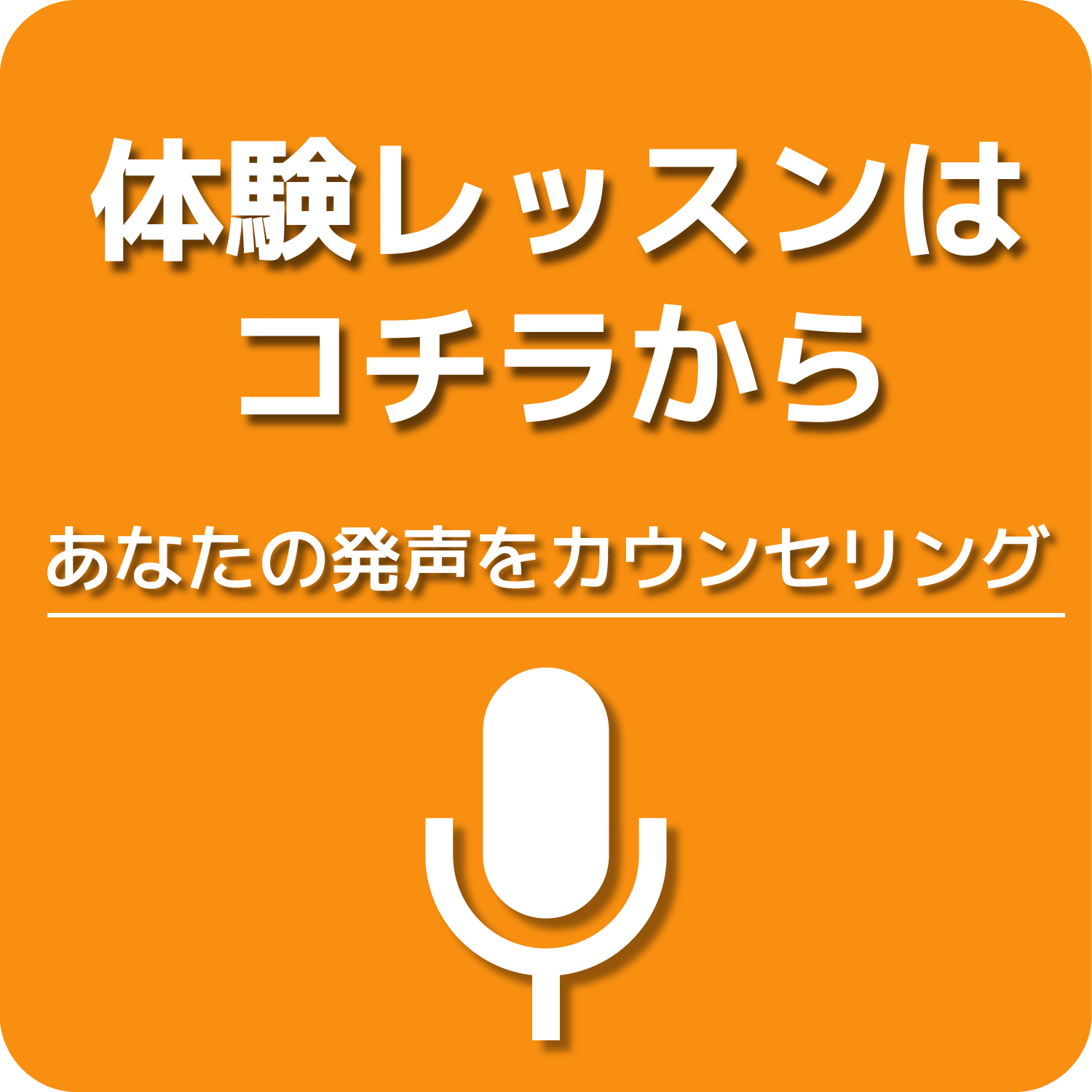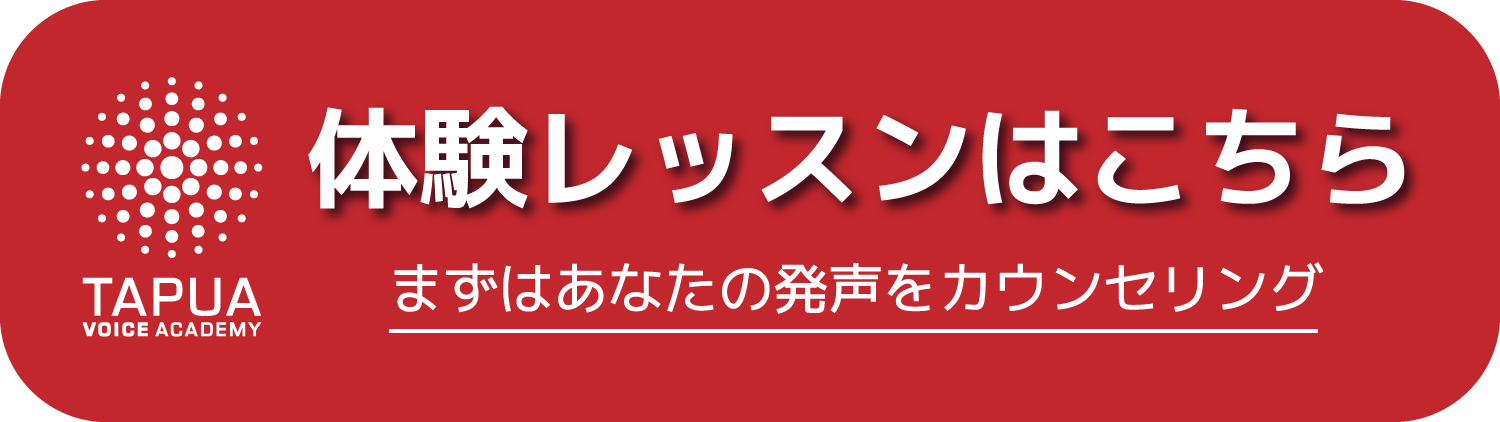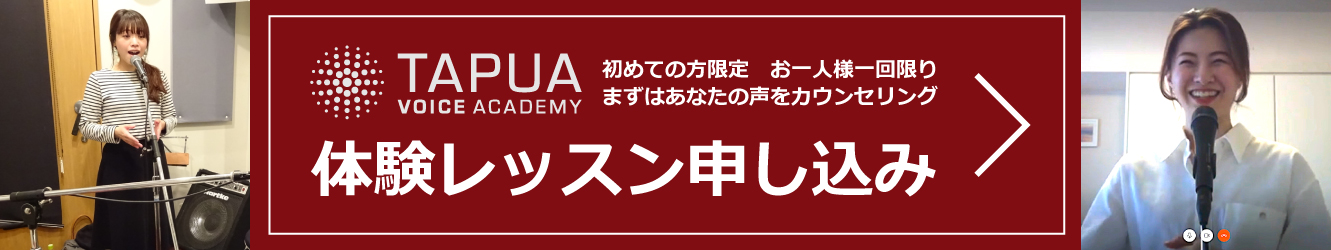ヘッドボイスの出し方:高音を自在に操るテクニック

私が学んだハイトーンボイスの秘密
どの時代においても、「ハイトーンボーカル」は多くのボーカリストの憧れの的です。
「突き抜けるように高い声を出したい」という願望は、多くのボーカリストが共有する夢です。
私も例外ではなく、中高生の頃からハイトーンボーカルに強く憧れ、試行錯誤を繰り返してきました。
しかし、20歳を過ぎても「海外アーティストたちのハリのある高音を出したい」という願望に対しての解決策を見つけれれず、「自分と彼らとの違い」も「その原因(理由)」さえ分からないまま、挫折感を抱えつつ歌い続けていました。
二人の名コーチとの出会い
1995年の夏、当時の私の音楽活動を応援していただいていたKenji Sano氏(ロサンゼルスと日本に拠点を置くベーシスト、ミュージック・ディレクター。カラパナのリーダー)の案内で、世界的に著名なボイストレーナー、セス・リグス氏のプライベートレッスンを受ける機会を得ました。そして、そのレッスンを通じて、長年の未解決案件であった「海外アーティストたちのハイトーン」を支える発声法を学び、習得することができました。
その数年後、グラミー賞受賞シンガーTori Kellyなどを指導する全米トップボイストレーナー、ビリー・パーネル氏(2007年よりタプアの特別監修役マスターティーチャー)と出会い、さらに細かな発声と歌唱のテクニックとメカニズムを学びました。これにより「日本人シンガーと海外シンガーのハイトーン(高音の発声)の決定的な違いとその原因」を理解し、その解決ポイントも明らかになりました。
両氏との出会いを通じて、様々な声の響きを学び、その中でも特に重要なのが「ヘッドボイス」です。高音域を出す際に限らず、『歌の表現の幅を広げるため』『ミックスボイスの習得』には特にこの技術が鍵となります。
ここでは、ヘッドボイスを正しく響かせるために押さえるべきポイント、ヘッドボイスを響かせるまでのアクションを書き出します。
ヘッドボイスの基本的な発声ポイント
ヘッドボイスが出るまでの流れ
1.喉を開く(オープンスロート)
喉を開いた状態(オープンスロート)での発声が絶対条件です。
2.音程の上昇のさせ方
低音→高音へと音程を上げていくとすれば、チェストのまま引っ張り上げて音階を上昇させるのではなく、「あくび」をするように、息を吐き上げながら声を出し始めます。
そして、音程が上がるにつれて、声の響きの位置が胸部、口腔奥、後頭部と移動していくことを感じるようにします。
3.低音域から中音域へのつなぎ目
音程を上昇させる際、低音域から中音域へ移る「切り替えポイント(1st.ブリッジ)」で共鳴が崩れないようにすることが大切です。そのために、喉の開き具合、ブレスの量のコントロール、そして響きを当てる位置(どのあたりを共鳴させるのか)のコントロールが重要になります。
おおよその共鳴ポイントの目安は、引き上げた軟口蓋の後ろあたりです。
4.中音域から高音域への移行
オープンスロートでの中音域のから高音域に切り替わるポイント(2nd.ブリッジ)では、響きが上咽頭と頭部にスムーズに移行するように、常にソフトパレットは上げておき、上咽頭内と頭部に向けてブレスをしっかり吐き上げます。
これらのアクションの流れを崩さず、「あくび」状態のまま低音から高音まで一切息を途切らせずに無段階(サイレンのように)発声する、という練習を繰り返すことで、ヘッドボイス(頭部で共鳴する響き)の感覚が捉えられるようになります。
ヘッドボイスの基本的な出し方と感覚
ヘッドボイスはその名の通り、「ヘッド=頭」を響かせる声です。声帯がある「下咽頭」で強い響きを作る音ではありません。しかし、すべての音程の声が声帯の振動音を原音としている点は変わりません。
では、どうやって声帯で発生した振動音を頭で響かせるのでしょうか?
答えは、「吐く息(ブレス)」を使って声帯振動音(空気の揺れ)を頭部まで吐き上げることです。具体的には、目一杯拡張させた上咽頭や鼻腔に息を吐き込み、両空間を共鳴振動させることでヘッドボイスが生まれます。
「高い声を出すのが苦手」「ヘッドボイスを出そうとすると喉が詰まった感じになる」という方の多くは、「発声のセオリー」としての「息を吐く」という行為を疎かにしがちです。「吐く息(呼気)」は発声全般において「原音を発生させる動力源」です。
ヘッドボイスを出すためには、特に「吐く息(呼気)」が重要であることを忘れないでください。
この発声の感覚をつかむためには、次のようなアクションが役立ちます。
「たっぷりとゆったりと息を吐いて柔らかなハミングの響きを作り、それを口腔内から上咽頭や鼻腔の全域で共鳴させる」
この発声は、気持ちをリラックスさせた状態なら誰でも出来るアクションです。イメージとしては、「深呼吸をしながらハミングする」という感覚です。
この「深呼吸ハミング」で低音から徐々に音階を上げていくと、「鼻から息と声が吹き抜けて行くことで頭部が共鳴振動する」という体験ができるはずです。
そして、それがスタンダードなヘッドボイスの出し方と感覚と考えて良いです。
ヘッドボイスを出す際の注意点
ヘッドボイスの発声が正しい場合、喉への負荷や締まるような苦しさはほとんど感じません。
むしろ、「喉が締まるような苦しさを感じた段階で、すでに声の出し方を間違えている」と考えてください。
ヘッドボイスを正しく発声できている時の感覚は、鼻の奥や上咽頭への呼気の圧力感とともに、頬骨や眼底の奥、後頭部や頭頂部にかけて内部からの振動を強く感じるはずです。
ヘッドボイスは中音域でも使われる
一般的に、ヘッドボイスの目安音域は
・ 女性のヘッドボイス: F5~G6(国際表記)
・ 男性のヘッドボイス: B4~G5(国際表記)
(※上記の音階番号はミドルCをC4として数えた番号です。鍵盤の音階番号表記は楽器メーカーによって若干異なる場合があります)
と言われています。
しかし、厳密に正しく解説すると、ヘッドボイスは「高い音階の声」だけを示すのではなく、どちらかといえば「頭部の響き(共鳴音)をメインにした声、その響きを出す発声テクニック」を示します。
ヘッドボイスが高い音階の声に限られない理由は、上記の目安音階より下の音階、つまり中音域でもヘッドボイスの響き(ヘッドサウンド)を使っている楽曲が多く存在するためです。
特に洋楽においては、邦楽に比べてこの傾向が顕著です。洋楽では発音の関係上、子音のバリエーションが多く、歌唱の際に排気音を多用することが多いため、中音域でもヘッドボイスの響き(ヘッドサウンド)を使うことが多いのです。
ヘッドサウンドを使っている楽曲の例
以下の楽曲では、中音域でもヘッドサウンドを使用しています。これらの動画を参考に、頭部側の共鳴をメインにした声の響きを聴き取ってみて下さい。
Ed Sheeran - Afterglow [Official Performance Video]
Earth, Wind & Fire - After The Love Has Gone (Audio)
The Stylistics - You Are Everything (Official Lyric Video)
これらの歌唱を聴けば、「中音域でのヘッドサウンド」と言っても特別なものではなく、洋楽でよく耳にする歌声(響き)だと分かると思います。
ヘッドボイスを習得するコツ
『ヘッドボイス』は単に高い音階の声を指すのではなく、『頭部寄りに共鳴させる発声テクニック』を意味します。この理解を持つことで、ヘッドボイスの習得が容易になります。
そして、重要なのは、どんな曲を歌うためにヘッドボイスを出すのか、曲ごとにてヘッドボイスの強弱をどう付けるのかを考え、『ヘッドボイスを鳴らして歌うフレーズ』のイメージに近づけるように練習することです。
ヘッドボイスを習得するためには、ヘッドボイスを多用している楽曲を選び、その曲を歌っているアーティストと同じように歌えるようになることを目標にする練習が効果的です。
このような取り組み方が、ヘッドボイスの練習含むボイストレーニングレッスン全般において、最も効果的だと思います。
ぜひ、ヘッドボイスの良いお手本になる楽曲をたくさん聴きながら練習してみて下さい。

タプアヴォイスアカデミー
Takayoshi Makino